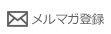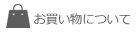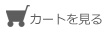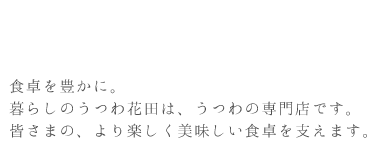色、冴える。
― 高島 慎一(京焼)池島 直人(古九谷)色絵展を控えて ―
2月21日(木曜日)に初日を迎える「高島慎一、池島直人色絵展」を前に
二人の工房がある京都市今熊野、石川県山代温泉にそれぞれを訪ねた。
花田にとって二人の個展は初めてのこと、
長い歴史に育まれてきた日本の代表的な色絵
『京焼』『古九谷』をベースにして
現代生活に向けたうつわ作りに邁進する
二人の共通の姿勢から企画された展覧会である。
京焼といえば鮮やかな色絵磁器を連想しがちだ。
しかし京都考古資料館を訪ねてみると色絵染付だけでなく
織部 薩摩 唐津等の陶片も市内の発掘品として陳列されている。
何といっても京は一千年を越える都、時の権力者や富豪の物欲を満たすため
窯元や商人達は競って全国の名立たる産地のものを
倣って納めたにちがいない。
その中でも薄手で色鮮やかな黄交趾、緑交趾を中心とした色絵磁器は
“京の都に相応しい優雅”を演出する為 最も効果的な焼き物として
京焼の代表格となって来たのだろう。

高島 慎一氏は「洸春窯」三代目当主洸春を15年前に襲名した。
高島家はもともと愛知県瀬戸で代々窯業を営んでいたが
明治中期 曽祖父の代に京都に移転する。
祖父が「洸春窯」を起こし
由来 三代に渡り色絵専門の窯として確乎とした地歩を固めてきている。
祖父の代は割烹中心のうつわ制作であったが
先代から一般家庭の日常食器を幅広く手掛けるようになった。
出品作の中で マグカップ、急須、ポット、銘々皿が中心をなしているのも
そうした需要に応えてのことだろう。


京の文化と言えば堅苦しいまでに伝統を重んずるという印象がある。
先代は 生前 次代を担う高島氏に折に触れてこう諭したという。
『基本的な精神、技術は代が変わっても 磨き 継承していかねばならない。
しかし人が変われば時代も変わるしセンスも変わる
決して伝統に埋没することなく新感覚にチャレンジしなさい。』
ここには形骸化したかたちに固執するものではなく
刻々と変容する時流にも的確に対応して行こうとする
しなやかな京文化の本流の姿をみるのである。
高島氏はかたち、色に妥協することはしない。
事実 以前には無かったトルコブルー、濃紺を新たに開発し
『新たなる色絵の展開』を予感させる。

高島氏は日常食器を作るうえで
一番重視したいのは何といっても『使い易さ』と断言した。
うつわを掌に包んだ時、如何に馴染み 和むかということだ。
この確固とした信念が貫かれている限り高島氏の仕事は
我々の食卓により安心した華やかさを与えてくれるに違いない。
一方『古九谷』は江戸初期に勃興し
五十余年の僅かな時を経て忽然と消えてゆく。
実にミステリアスな話だ。
今回の企画展でもう一方を担当する池島直人氏は
古九谷誕生の地近くの山代温泉内に工房を構えている。
古九谷の特徴は大胆、斬新な色調と文様で表された
わが国では群を抜いたスケールの大きさにある。
池島氏の手になるうつわを見ていると
青手を中心とした深みのある色遣いは古九谷を彷彿とさせるものがあるが
文様は大胆というより
氏独特の達者な筆力を活かした繊細なものが顕著だ。


このことについて当人に聞いてみると
寡黙な氏は朴訥ながら
「古九谷の雰囲気は確かに好きだが
意識の上では決して倣おうとか肉薄していこうなどとは思っていない。
寧ろ今までに無い独自の世界を作り上げて行きたい。」
と強調する。その上で
「今まで色絵具も様々調合しながら
青手をベースとした自分自身の色調を狙ってきた。
文様も含めて揺るぎない雰囲気の中にも
柔らかな感じ 動きのある愉しい感じを出していきたい。
挙句 将来的には洋絵具も使った違う世界にも踏み出したい。」
と眼を輝かせる。


今回の展覧会では特に注目してもらいたいアイテムとして
石畳文様や全面緑で塗られた銘々皿を挙げた。
他にはない一見使うのが難しそうなうつわだが
なかなかどうして使ってみるとこれが面白い効果を発揮すると
胸を張る。
高島 慎一 池島 直人
共に日本古来の伝統的な焼き物に身を寄せながら
現代生活をより華やかに彩っていく色絵磁器の制作に没頭する陶工。
お洒落な最新作の数々が展観される日が待たれる。
尚 今回は池島直人夫人 仁美さんの色絵も出品される。


伝統的なものとは離れた創作文様だが
醸し出す軽妙洒脱でチャーミングな表情にも注目して頂きたい。