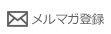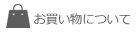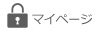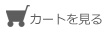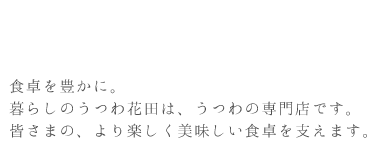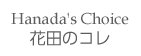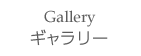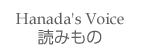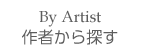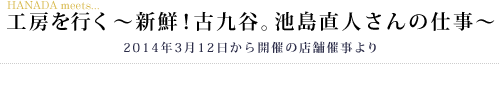
金沢、加賀方面に 出張した時のことです。
宿泊したホテルのロビーの一隅で 焼き物を始めとするガラス 木工など
数名の地元工芸家による小品展が開かれていました。
金沢、加賀と言えば 工芸の本場 どれを見ても 伝統の技や心を基調に
現代センスにも溢れた力作揃いです。
その中で 私を もっとも強く惹きつけたのは
古九谷の手法に倣った 池島直人さんの作品です。
吸い寄せられるように その前に立っていた私は
今まで眼にしたこともない古九谷の新鮮な魅力に囚われていました。
私には 予てから 決めていることがあります。
「 日本の焼き物の中で
世界に一番誇れるもの それは何ですか」
という問があれば 躊躇なく「古九谷」を挙げるということです。

青手椿図平鉢 古九谷
石川県立美術館発行「九谷名品図録」より
古九谷は 実に 謎の多い焼き物で 江戸時代十七世紀半ばに
加賀九谷の地で生まれ 五十年の時を経ずして
十八世紀初めには 忽然と消えていってしまう歴史を背負っています。
色絵磁器が 中心ですが 古伊万里、京焼きも含めて
その文様に於いても色調に於いても
日本の色絵の中では 大胆、斬新という点で 群を抜いている存在です。
他に例を見ない大らかで華麗な意匠は
観る人の心を 強く 魅了してきました。
ところがどうでしょう、
池島直人さんの古九谷の模しは
色彩の華やかさに於いては古九谷そのものですが
文様や骨描き(黒で描かれる文様や輪郭を表わす線)には
古九谷の奔放さはなく繊細でペルシャ文様さえ思わせる瀟洒な表情なのです。


正に新境地の古九谷です。
池島直人さんの仕事はこの独特な切り口で展開しています。
工房が山代温泉の 街中にあると聞いた私は
時を置かずして訪ねて行きました。
店舗を兼ねた工房で 池島さんはにこやかな表情で迎えてくれました。
京都で生まれたこと
小学校入学時に陶工であるお父さんの郷里 片山津に移り住んだこと
高卒と同時に京都に戻り陶芸の修業に入ったことなどを
淡々と 話してくれました。


三十九歳になった今、九谷焼ゆかりの地に あって
古九谷の象徴的な 青手(深みのある緑と黄の色調)を中心に
楽しい、使うことがそそられるようなをうつわを
作っていきたいと眼を輝かせます。
修業した京都の雅美あふれるセンスを加味した
「新鮮!古九谷」の誕生は
私たちの食卓に今までにない鮮やかないろどりを添えてくれるでしょう。
池島さんの特異な経歴とセンスが
花田で見事に開花することを願わずにはいられません。

今後の活躍が楽しみです。
■企画展名
魅惑のオムニバス -旬の実力派、競演-
■開催期間・場所
期間 : 2014年3月12日(水)~ 3月22日(土) ※期間中無休
場所 : 「暮らしのうつわ 花田」 2Fギャラリースペース
■参加作家
イム サエム、正木春蔵、林京子、中山孝志、中尾万作
花岡隆、岡田直人、岡本修、余宮隆、池島直人 他多数